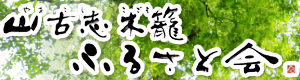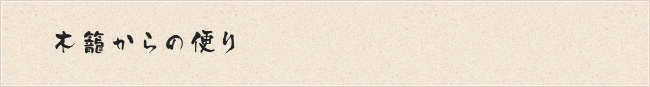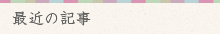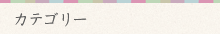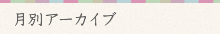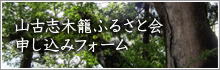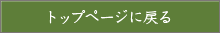春の行事日程
例年より早く残雪も消え、郷見庵も4月10日にオープン致しました。当日、ふるさと会役員会を行い、春の行事計画を決定いたしましたのでお知らせいたします。
1、春の道普請及びふるさと会総会 5月1日(日)
・道普請 9時より (ふるさと会会員は集落内の道路のゴミ拾いを行います)
・ふるさと会総会 10時半頃より(道普請が終わり次第総会を行います)
2、田植え 5月21日(土) (詳細は別途HPでご案内いたします)
3、チマキ、笹団子作り 6月26日(日) (会費制となります。詳細は別途HPでご案内いたします)
無事、春の行事ができることに感謝の気持ちをこめ、皆様をお待ちしております。
兵庫県丹波市のみなさん頑張って!
今日は平成26年の水害で被災された丹波市の皆さんと復興への懇談会をしました。今日来られたみなさんの住んでいる地域は、地形も山古志と似ていることから、「山古志周辺を復興のモデルにしたい」とおっしゃり、水害直後に訪問され、今日で4回目の訪問という方も。特に今回は、「女性たちが何か活動を始めよう!」と郷見庵を切り盛りする集落のお母さんたちや、ふるさと会のメンバーとお茶を飲みながらのお話しとなりました。
名物の神楽南蛮味噌おにぎりと、牛汁のお昼に話も弾みます。もうすぐ木籠ではお釈迦様の日なので、縁起物のお釈迦様のお団子も頂きました。
松井さんの奥さんキミさんは、「木籠はこれからどんどん人が少なくなる。かといって、ここに住んでくれというのは難しい。だったら、ここを人に来てもらえるような場所に、ここに人を呼べばいいんだよ」と、いつも故松井会長が言っていたとお話ししていました。人が集まって楽しめる場所、人がまた来たいなと思えるあったかい場所。「だから、郷見庵は冬場を除いて年中無休なんです。ここに来れば、必ず誰かがいて、お話しして、お茶のみができるように。それからメンバーがそれぞれの得意分野で自分たちも楽しめる場所なんですよ」
最後にみんなで記念撮影。今日は青空。たくさんの雪だるまに囲まれて、みんな笑顔。丹波市のみなさん、これからもいっしょに頑張りましょうね!
賽ノ神
1月10日、今年の初行事「賽ノ神」を行いました。例年にない小雪。市内では十分な雪がなく、行事を見送った地域もあるようです。ここ山古志木籠では、みぞれまじりではありましたが、大勢の方々が集まってくださり、今年の無病息災をお祈りすることが出来ました。
賽ノ神の組み立てから藁あみ、おんべ作り、みんなが協力して教えたり、習ったりで準備が進みます。
今年は、おんべとともに、天国の松井さんへのメッセージを添えました。そして、「ふるさと」と「アメージンググレイス」の素敵な歌声。ありがとうございました。
またフクロウでおなじみの溝口さんご家族が来てくださり、木彫りの松井さんが届けられました。温かいお言葉を頂き、松井さんご家族へも手掘りの福の神。これからこの松井さんが、木籠をずっと見守ってくれることでしょう。
いよいよ賽ノ神に点火です。モクモクと煙を上げて天まで燃える賽ノ神。恒例の餅つきで、つきたてのお餅をほおばりました。特製小豆や牛汁のお雑煮も最高です。賽ノ神の火で体を温めながら、スルメや切り餅焼き。束の間の青空に、錦鯉の凧も空を舞いました。みかん撒きが始まると、やっぱり子供は雪の子!素早い動き。盛りだくさんの催しに、そろそろ終わりも近づいたころ、賽ノ神の火を囲んで、みんなで「ふるさと」を歌いました。
集まってくださったみなさん、本当にありがとうございました。今年も、木籠を皆さんのふるさとと思って足を運んでください。こころよりお待ちしています。
賽の神の予定
年明けの10日(日)に、五穀豊穣、一年の息災を祈念する小正月の恒例行事、賽の神を行ないます。
朝、10時から集落の住民の皆さんと一緒に賽の神作りを始めます。
皆さんからも賽の神の組み付け、てっぺんに飾るおんべ作り等も参加いただきたいと思います。
賽の神が出来上がり次第、11時ごろから餅つきを行い、つきたての餅を食べてから賽の神の点火となります。
(来年の年男、年女となられる申年の方に点火の役をお願いします)
点火後は餅やするめを焼いてお楽しみ下さい。またみなさんとお会いできることを心よりお待ちしています。
尚。今回、故松井治二さんの木像を山古志の桐の木で、埼玉の会員溝口さん(ふくろうの彫刻でおなじみの)が
彫って下さり、当日、披露して下さるそうです。
紅葉の秋空 蕎麦打ち大会
11月1日、木籠はすっかり茜色に染まり、青空とのコントラストがきれいな一日でした。恒例の蕎麦打ち大会の日。木籠の畑で暑い夏を乗り切り、蕎麦摘みから粉ひきをしてみんなで手間暇かけて仕上げた、木籠ふるさと会産のそば粉です。
蕎麦打ち自慢の会員さんの手ほどきで、自分で打ったお蕎麦を楽しめます。外の窯でゆでたてのお蕎麦を冷たい水できゅっと引き締め、お母さんたち手作りのてんぷらを添えて召し上がれ。
今年は、お蕎麦の繋ぎもいろいろでした。ふのり(海藻)蕎麦、ジネンジョ(山芋)蕎麦、茶蕎麦など。バラエティー豊富に、チームワークも上がって、もちろん腕も上がりました。たくさんの方に召し上がっていただきありがとうございました。ふるさと会のメンバーも、秋の味覚にホット一息。忙しい冬支度前の楽しいひと時でした。
11年目の震災記念の日
今年も10月23日がやってきました。中越震災から11年目、木籠は朝日に照らされて、少し色づいた山々がきれいでした。芋川の近くに行くと、ささやかな川の流れが聞こえてきた。水没家屋の保存作業が行われていました。福島の桜の葉も秋色でした。
朝10時ころからたくさんの仲間が郷見庵に集まります。それぞれが協力して震災記念日の準備がはじまりました。アツアツのおにぎり、さつま芋堀り、どっしり重い杵や臼もでてきましたよ。今日一日、心を込めておもてなしです。
平日だというのに、大勢の方々が足を運んでくださいました。今年は角突きの牛やポニーもお出迎え。恒例の餅つきに腕をふるい、つきたてのお餅はあんころ餅ときなこ餅で召し上がれ。山古志ならではの牛汁と神楽南蛮みそのおにぎり。朝堀りたてのさつまいも。口いっぱいにほおばって、今がある幸せを分け合いました。
凧揚げ名人の会員さんは、錦鯉の凧を披露してくださり、また松井さんと木籠で今年お亡くなりになった3人のお年寄りの方々へ、追悼の気持ちを込めて、郷見庵2階から発泡スチロールで作った白い鳥を木籠の空に放ちました。松井さんや懐かしいお年寄りたちの笑顔が見えるかのように、皆で空を見上げて舞い降りる鳥に手を伸ばしていました。
震災でつながった皆さまとのご縁と今の幸せに感謝し、これからいろんな難しいことがあっても、みんなでなんとかやっていけると気持ちを新たにした一日でした。これからも、山古志、木籠、郷見庵に来てくださいね。だれもがホットできるよう、皆でお待ちしています。
蕎麦打ち大会 11月1日(日)になりました!
本年の蕎麦は昨年並みに10㎏程度の収穫がありました。
11月中旬に予定しておりました恒例の蕎麦打ち会は、都合により前進して11月1日に下記のように行うことになりました。
1・日時、場所 11月1日(日) 10時より木籠集落公民館にて
(蕎麦打ち体験をしたい方は10時までに参集)
2・会費 500円 (てんぷら付そばが召上がれます)
年々、蕎麦打ちの腕が向上して美味しい蕎麦が打てるようになりました。
参加下さる方の連絡をお待ちいたします。
脱穀を終えて「ふるさと会米」できました
10月10日、朝方長岡にかなりの雨が降り、どうなることかと思った朝でした。
山古志に行ってみると、雨を見越してプロ集団が集結、昨日のうちにはざから稲束をすべて降ろしておいてくださったということでした。お見事!おかげでカラッと太陽に干された稲束の脱穀作業をすることができました。
脱穀作業もやっぱりチームワーク!稲束を降ろして、運んで、手渡して・・・何をするにも相手が受け取りやすいように、次の作業がスムーズに流れるように。脱穀機にも入れやすいよう、そろえて横で並べます。夫婦さながら息が合っておりました。子供たちも、女性陣もなかなかの力持ちです。黙々とひたすら稲束を運んでくれました。ご苦労様でした。
どんどん出てくる稲藁もその場で手早く束ねます。万能で大切な山の資源です。こんな風に即席箒にもなっちゃいます。散らばった稲や籾を上手に集めて最後の最後まで無駄なく脱穀機にかけました。軽トラック2台分。何袋になったのかな~。今年もふるさと会のお米が出来ました。みなさんのお口に入るのももうすぐです。手間暇かけた分、一生懸命みんなで働いた分おいしく感じます。楽しみですね~\(^-^)/
10月23日震災記念の日 郷見庵感謝祭
震災11周年を迎える10月23日に今年も郷見庵感謝祭を催します。
本年のイベントの主な内容
1.山古志闘牛会の牛とポニーを郷見庵に招待し来場客との記念撮影 11時~2時頃まで
2.餅つき 12時頃
3.薩摩芋掘り体験 11時頃より随時 (掘った芋を格安でお持ち帰り頂く)
4.錦鯉凧、他の凧上げ 11時頃より (風の状況、雨天等により変更の場合有り)
5.その他 (検討中)
会員の方々のご協力と大勢いの皆様のご来場をお待ちいたします。
脱穀日変更のお知らせ
本日10月6日、大勢の方達に参加頂き蕎麦の刈り取りを行ってまいりました。11月の蕎麦打ち会で使用する量は十分収穫できたかと思います。
また、都合により 12日に予定していた脱穀作業を、10月10日(土)に変更することになりました。
参加を予定された方々には大変ご迷惑をお掛け致しますが、改めてご検討くださるようお願い致します。
又、前回のお知らせでは蕎麦の摘み取り作業も脱穀と分担して行うつもりでしたが、本日の作業で蕎麦の収穫作業が総て終わりました。皆様の本日のご協力に心より感謝いたしますと共に、脱穀日の変更についてご理解とご協力を頂ければ幸いです。
ご都合のつく方々のご参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。